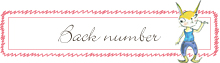- 1999.11.23 年報『女性ライフサイクル研究』
- 女性のトラウマと回復
女性ライフサイクル研究所 村本邦子
1990年の開設より、女性のトラウマは一貫して、私たちのテーマだった。もっとも、当時は、虐待という言葉を使っていた(子どもへの虐待、女性 への虐待というように)。虐待とは、権力構造を背後にした人権侵害であり、トラウマをもたらす。トラウマは、もともと外傷を指す語だが、心の外傷にも使わ れ、心的外傷と訳されたりもする。私自身は、トラウマを心的外傷と身体的外傷に分けて考えることはできないだろうと思っている。トラウマとは、存在を脅か すほどの傷つき体験であり、身体的外傷を伴う場合も、伴わない場合もあるが、心的外傷は常に存在する。よって、トラウマはあえて訳さず、片仮名表記のまま にした。トラウマをもたらすのは虐待に限らないが、本特集では、女性にたいする暴力、あるいは虐待の結果としてのトラウマにテーマを絞っている。
常に必ずとは言わないまでも、男性中心の社会では、男性が公的領域を担い、現実(リアリティ)を構成する一方、女性と子どもは私的領域に属し、男性の空 想(ファンタジー)の登場人物となる。女性や子どもへの暴力の多くは、私的空間において行われ、仮にそれが公的な空間で起こったとしても、目撃者がそこに 介入しようとしないのは、それが現実を構成する公的空間とは別次元の空間で起こっている場面として認知されるためだ。「本来、目にすべきものでない場面を 見てしまった。これは幻だ。見て見ぬふりをしておこう。」というわけだ。つい最近まで(ひょっとすると今なお)、誰かが殺されて、戸籍の抹消という否定し がたい現実的帰結をもたらすまで、親子やカップルの暴力には警察も介入しなかったではないか。この意味において、フロイトがヒステリーの原因をトラウマに 求めたすぐ後で、これを少女たちのファンタジーであると改めたことを理解するのはたやすい。公的領域は基本的に公正でなければならないために、不正はその 柵の外へ追いやられる運命にあるからだ。
虐待がファンタジーの一部である限り、被害者は、リアリティのなかに主体を回復、もしくは獲得することができない。多くの虐待には秘密の強要と解離が伴 うから、被害者は、それが本当に起こったことなのか、空想だったのか確信を持てないまま、生き続けなければならない。加害者とて、同じだろう。自らの行為 が白日のもとにさらされ、責任を問われない限り、半身をファンタジーの闇に埋めたままであるわけだから。第2次フェニズム運動は、「個人的なことは政治的 である(The personal is political.)」をスローガンに掲げたが、私的領域と公的領域を結びつけて初めて、女性や子どもへの暴力が現実として集りだされたのである。
傷ついた女性たちの回復は、トラウマとなった体験がリアリティの一部に組み込まれること、それはつまり、社会から認知されることを要求する。90年代に 入って、子ども時代の性虐待を告発する講演会の多くで、サバイバーたちがカミングアウト(自分の経験を皆の前で公表する)する場面に出会ったが、それは、 まさに、自分たちの体験を公的領域に属する事実として告発し、ファンタジーをリアリティヘと転換させる意味と力を持つものだった。これらの事実は、トラウ マからの回復が、従来の面接室における個人療法だけでは不十分であることを示している。伝統的な心理療法は、「心的現実」という言葉をあてることで、ファ ンタジーをリアリティに転換する力を与えてきたが、少なくともトラウマ被害者に関する限り、これは無効である。私的領域から抜け出ることのできない出来事 が「心的現実」と呼ばれる限り、それは「嘘」と同義語だからだ。そうすれば、治療者は、自分の世界を脅かされずにすむ。しかし、それは、「社会的現実」と して認められることを求めている。
この十年、女性のトラウマに対する認知は徐々に高まり、我が国においても、新聞やテレビで取り上げられる頻度が増え、被害者支援体制が整えられつつあ る。女性や子どもへの暴力がようやく公的領域の現実として認知され始めたことを示すが、その陰に、変化を求めて闘ってきたサバイバーおよび支援者たちの力 を感じずにはいられない。私たちが関わってきたのはこの十年だが、その前の十年、そのまた前の十年にも、この問題に取り組み続けた粘り強い先輩たちの力が あったにちがいない。歴史を構成するのは現実であり、リアリティとなり得て初めて、それは歴史に組み込まれる。トラウマからの回復は、個人史および歴史の 書き換えを要求するだろう。大量虐殺さえもファンタジーにされかねないことを思えば、私たちは歴史に敏感でなければならない。もう二度と、女性たちの闘い の歴史を抹消させてはならないと思う。
今回の特集は、以上のようなことを心に刻み、傷ついた女性たちの現実を白日のもとにさらし、リアリティとして社会へ告発するものである。また、虐待と傷 つきのメカニズムを明らかにし、より有効な援助法を模索しようとするものである。今年は、ハーバード大学/ケンブリッジ病院暴力被害者プログラム主任のメ アリー・ハーベイ氏のご好意により、「生態学的視点から見たトラウマと回復」を所収することができた。「生態学的視点」とは、聞き慣れない概念かもしれな いが、コミュニティ心理学の用語であり、人や人の心にのみ焦点をあてるのでなく、コミュニティのなかの人、コミュニティのもろもろの資源や要因と相互関係 を見ようとする視点である。女性のトラウマと回復を社会の文脈のなかで捉えることの必要性は、すでに力説したつもりだが、「回復」を多次元的な現象とし て、7つの項目によって定義している点、重要である。
このように多次元的な視点をもちながらも、個から社会へと視野を拡げていけるように配列した。Ⅰ章は事例中心に、Ⅱ章は理論中心にまとめてある。Ⅰ章、 佐藤紀子氏の「ひらめ」では、リアリティがファンタジーに力を与え、力をもったファンタジーが、再びリアリティヘと作用するあり様が明確に見てとれるだろ う。ハーベイ氏の分類によれば、これは臨床的治療を得た例であり、吉村薫は、インタビューによって、治療的介入なしに回復へ向かった例を描いた。窪田由紀 氏の事例は、個人療法を中心にしているが、大学教員による学生の援助と学生相談という、基本的にコミュニティ介入のベースから個人療法へつなげられている 点に着目したい。
Ⅱ章、川喜田好恵氏と中村彰氏は、ドメスティック・バイオレンスに焦点を絞り、ジェンダー構造のなかで、いかに被害者と加害者がつくられていくかを分析 したうえで、援助の方法についても述べている。男性たちもまた動き始めていることを知って、心強い。長谷川七重氏は、ドメスティック・バイオレンスのなか でも言葉の暴力に焦点をあてた分析を行っている。子どもの虐待も同じだが、どうしても世間ははっきりと目に見える形の暴力にのみ反応しがちであるが、トラ ウマとは、存在を脅かす傷つきであることを繰り返しておきた」窪田容子は、治療者の立場から、中立性について再考した。トラウマの治療は、伝統的な治療の パラダイムの転換を迫るように見えるため、これに抵抗する治療者は少なくない。しかし、私の考えでは、中立性はじめ、従来の概念をトラウマという視点から 練り直すとき、(はやりの言葉で言えば)臨床心理学は「進化」する。
Ⅲ章は、主に電話相談という回路で、傷ついた女性を支えようとする立場のものをまとめた。平井三鶴氏は、徳島県の「女性サポートダイヤル」を通じて関 わった女性たちの現実を紹介している。相談者の住む社会と陸続きの社会/現実を生きる援助者の姿が目に見えるようである。窪田も触れている「代理受傷」に ついて真剣に考える必要があろう。前田真比子氏らは、ある機関の電話相談での体験をもとに、性被害についてまとめてくれた。ハーベイ氏も指摘しているよう に、コミュニティのなかの危機介入的な相談電話が果たす役割を痛感させられる。周藤由美子氏は、「性暴力を許さない女の会」の紹介と支援のあり方への提起 をしてくれた。会の方々とは、個人的なおつきあいはなかったが、よく講演会などのフロアでご一緒した。ボランティア・ベースでこんなグループが息ながく活 動していること自体、頼もしく、励まされる思いである。
IV章では、主に共生の視点での援助を紹介した。新恵里氏はアメリカでの研修の体験をまとめてくれた。さすがに、アメリカの被害者支援機関はずいぶん先 をいっているようで、地域の犯罪被害者センターが、まさに多次元的な援助を提供している様子が伺われる。アメリカならではの問題もあるようだが、「被害 者」と「加害者」の捉え方は参考になるだろう。前村よう子は、キリスト教の背景を持つ「ミカエラの家」を取材し、トラウマと宗教の関わりをまとめた。きっ かけは、前村自身の否定的な宗教体験だったが、この取材をきっかけに、彼女自身がある種の「癒し」を経験したようで嬉しい。取材を受けて頂いたシスターに あらためて感謝したい。「スピリチュアリティ」は、私自身、これから練り上げていきたいテーマである。高松里氏はセルフ・ヘルプグループについて書くと同 時に、専門家批判をしている。「トラウマは治療も回復も不可能であり、専門的援助は無力である」と主張するこの論考は、いささか挑発的であるが(なにし ろ、これはトラウマと回復の特集である)、その内容には頷ける。今一度、ハーベイ氏の論考に立ち返り、回復の定義と、回復にいたる道に専門家が寄与できる 可能性は一部にすぎないこと、専門家が関与しても回復にいたらない可能性、よけいに傷を深める可能性があることを想起すべきだろう。高松氏自身は、このセ ルフ・ヘルプ・グループのメンバーであるから、当事者であると言うことにも頷ける。ただし、私自身は、専門家としての役割を捨ててはおらず、状況に応じて 役割が変わることはあっていいと感じている。状況に応じて娘であったり、母であったり、妻であったりするように、私は、状況に応じて、専門家であったり当 事者であったりする。そのことに、あまり矛盾を感じていない。
最後のV章は、社会とシステムに焦点をあてた。西順子は新聞記事を手掛かりに、性被害に対する社会の動きを追った。社会の変化にあらためて驚かされると ともに、西が指摘するように、子ども時代の虐待、性虐待に関しては、まだまだこれからというのが実感である。本特集においても、予定どおりに執筆できな かった事情もあり、成人女性への暴力に偏ったきらいがある。しかし、子ども時代の虐待による女性たちの生の声は、コラムの形で執筆して頂いたものの多くか ら聞こえてくるはずだ。平山真理氏は、刑事手続きにおけるとくに性犯罪被害者の扱われ方についてまとめ、イギリスの制度も参考に、問題提起を行ってくれ た。加害者への対応はもちろんだが、傷ついた被害者の回復を助けるような形で司法が機能するシステムが練り上げられていくことを望む。
最後になりましたが、いつも暖かく応援してくださっている皆様、原稿を寄せてくださった皆様、いつも私たちのために素敵なイラストを描いてくださるJunさん、そして地水社の皆さんに感謝いたします。